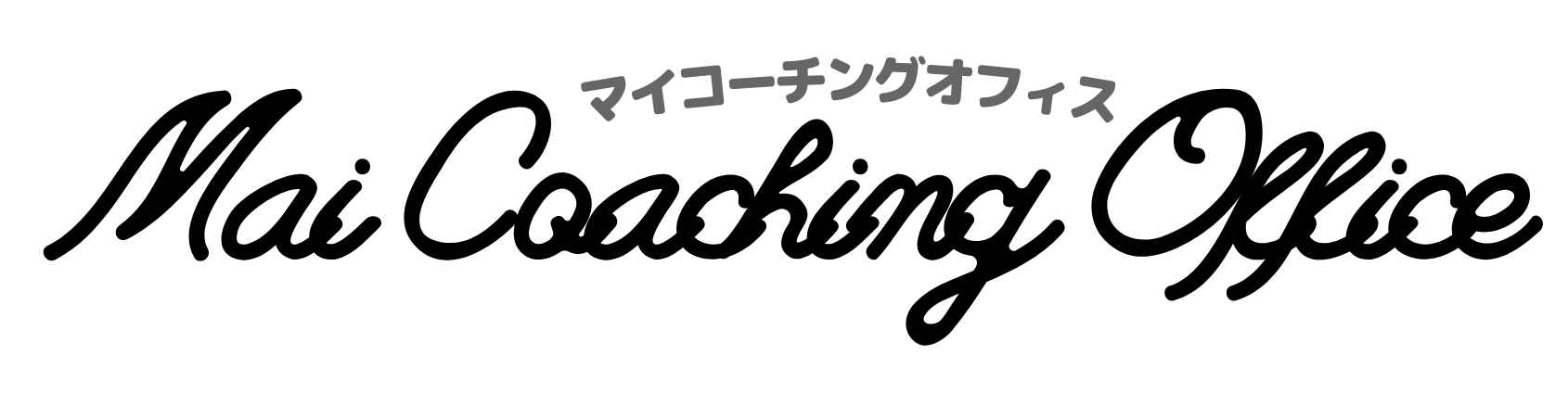マイコーチングオフィス事務局からお知らせです♪
9(月・祝)「習慣」のセルフコーチング① @ オンラインサロン
10(火) 無料セッション抽選日 @ ライン公式
23(月) 「習慣」のセルフコーチング② @ オンラインサロン
<今月のテーマ「私の楽しみ」について>まい先生より
あなたにとっての楽しみは何ですか?
楽しむことに関してのセルフコーチングは、まず「自分は人生を楽しみたいか?」という問いかけから始まります。そう問いかけないといけないくらい、私たちは、日々の忙しさや「やらなければいけないこと」または「努力や我慢」に慣れ親しんでしまって、「楽しむ」ことを忘れています。
楽しむと、人生が変わります。
日々の生活で、どうしたら「楽しむ」要素を加えることができるでしょうか?
あなたは何をしている時に「楽しい」と感じるのでしょうか?
「ここ最近、楽しいと感じられない」のなら・・何が要因でしょう?
この先、どんな楽しみをあなたの人生に取り入れていきたいでしょうか?
そうすることで、あなたの人生(日常や仕事)がどう変化していくのでしょうか?
一緒にセルフコーチングしていきましょう♪
まい先生(中村舞)/ コーチング&傾聴力の女王

マイコーチングオフィス代表。札幌在住。企業研修講師&プロコーチとして活躍(15年で5,000人以上を指導)。コーチングの要素を取り入れた思考力を引き出す研修や、傾聴力で個人の本質(自分軸)を引き出すセッションには定評があり、全国にクライアント多数。まい先生の名で親しまれている。